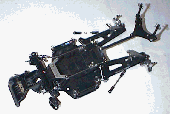
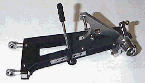
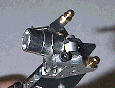
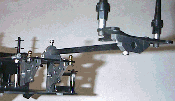
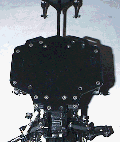
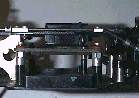
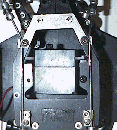
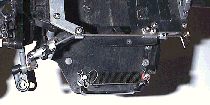
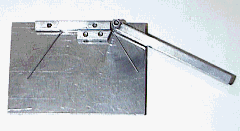
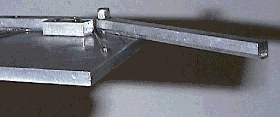
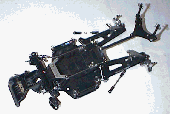
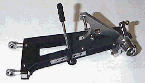
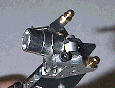
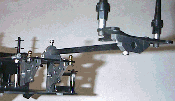
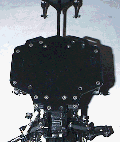
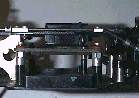
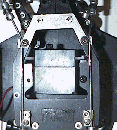
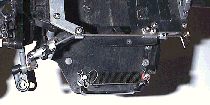
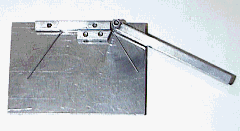
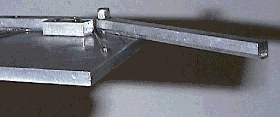
う〜ん、この車は説明することが多いなぁ。
さて、ここからが前代未聞の話。FF車がスタート時にトラクションがかからないのは、知っての通り。これはノーズリフトがおこるからですよね。それを防ぐために、重量物をフロントアクスル近くにマウントし、リアサスのピボットをフロントアクスル軸線上に近づけるわけです。でも、どんなに努力してもリフトはおこる。そこで、なにか物理的な力で、リフトを押さえ込んじゃえば…と思ったわけです。たどり着いた方法は、前後のサスアームをつなぐスタビライザーでした。ピッチングスタビライザー、アンチピッチングバーと(勝手に)呼びます。これが付いていると、フロントリフトがおきたとき、スタビがリアサスアームを押して、リアの車高を上げます。(前と同時に後ろもリフトさせる)路面に対するフロントアクスルのスキッド角が変わらないので、トラクションは逃げにくいという狙いです。結果からいうと、スタート時のトラクションについてかなりの効果があります。とりあえず、この車よりスタート時のトラクションがかかるFFを走らしたことは(かつての、神田スペシャルや、ラビットのFF含め)ありません。しかし、コーナリングでのテールブレイクに癖があって、なんとなく、この車もお蔵入りになりました。ちなみに左右のサスをつなぐ通常のスタビも同時に付けると、一輪上がっただけで、残りの3輪全てが上がります。妙な景色です。
もう一つ。ピッチスタビのおかげで、いくつもスタビを自作しなければならない自体が発生したわけですが、スタビを正確に作るのは結構コトなんですよ。まして、ピッチスタビは左右2つ1組ですから、精度の揃ったスタビが2つ必要となります。で、スタビ専用のベンダを自作しました。(治具ですね)これに、任意の太さのスタビを挟んで曲げるわけです。ピアノ線の方に曲げ位置を付けておいて、ベンダーの方には曲げ角を書いて(マジックで)おけば、かなり精度の揃ったスタビが作れます。
じゃあ、まず生い立ちから。見て判るように、ベースは田宮のFFツーリングカーです。レビンでした。このキットは、94年?の4月に、お馬さんに買ってもらいました(笑)。僕が参加しているデパート屋上レースは路面がタイルという難コースで、2駆はまともに走るのも大変という状況です。でも、FFなら…と思ったのが甘かった。やっぱりトラクションが掛からない。んじゃ改造ってことで、その年のゴールデンウィークに最初のシャーシができました。そのときは、バッテリー搭載位置はノーマルと同じで、リアサスだけトレーリングアームにしたものでした。でも、やっぱり走らない。で、エスカレートしてパッテリーを出来るだけ前に、リアアームを可能な限り長く、のコンセプトでたどり着いたのがコレです。
フロントのギヤボックスおよびサス関係はすべてノーマルのまま、シャーシ以後を自作しています。
リアアームは6mm角アルミ材にアルミボールリンクを付けて、ピボットをでっち上げ、2枚のFRP(この車、黒い板は全部黒く塗ったFRPです)でサンドイッチしたものです。アクスルは、セミトレーリングの固定アングルとは別個にキャンバー角が調整できるように(最終的に)しました。ピボットをリンクにするのは、精度をだすためのズルです。自作マニアの技量では、サスアームのピボット穴を正確に開けるのは不可能だと(僕は)思っています。
ボディは田宮のレビンやシビックを載せたので、どうしても後ろにボディマウントを設けなければならない。でも、重心を後退させるのはイヤってことで、カーボンシャフト(田宮F1用)にボディマウントだけ付けて、後ろに延ばすという手段を用いました。クランプ式(すりわり)のホルダーを作ったのはこれが初めてです。ロアとアッパーのデッキをつなぐポストも自作するハメになりました。
シャーシは、ステアリングワイパーの直後にバッテリーが載るだけのスペースしかありません。リアサスピポットはアスチュートのパーツです。
ステアサーボはバッテリーの上に置くしかないわけですが、アッパーデッキの上では、重心の高さが気になるし…ということで、本当にバッテリーのすぐ上まで落とし込んでみました。(実際に使ってたサーボはエルグ)
ピッチングスタビに効果があるのは間違いなく、さらに、コーナリングでの悪影響を最小限に止めるには、トレーリングアームというリアサス形式は合っていないと思います。この車の場合、先にトレーリングアームがあって、後からピッチスタビを付けたので、アワワになったわけで、まず、ピッチスタビを活かすコンセプトなら、4輪ダブルウィッシュボーンでしょう。実は、ノーマルの田宮FFにピッチスタビを付ければそれが一番のような気がしてるんですけどね…(くやしいからやらない。)